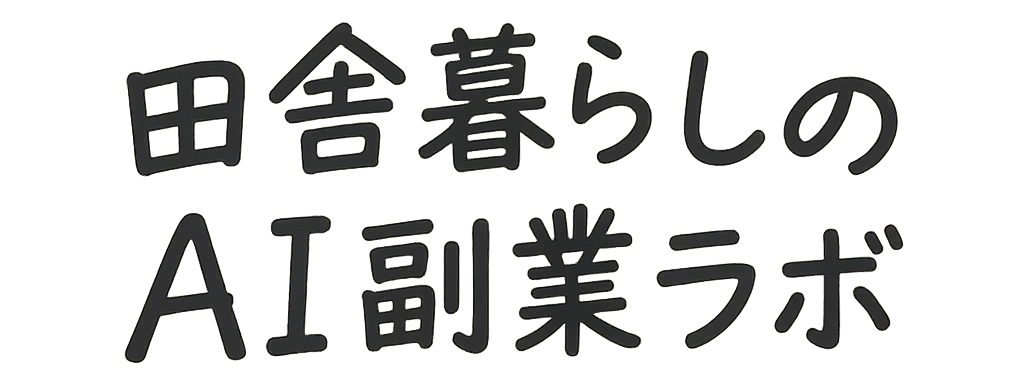はじめに
野生動物(イノシシ・シカ・サルなど)による農作物被害は、都市部から離れた地域だけでなく、郊外でも深刻です。そこで注目されているのがAIとドローンを組み合わせた害獣調査。上空から安全に・短時間で・再現性をもって探索でき、AIで解析すると「群れの出没パターン」や「侵入ルート」まで可視化できます。自治体、農家、猟友会、林業、建設現場の緑地管理など幅広いニーズがあり、副業としても成立しやすい分野です。
この記事では、完全初心者でも今日から準備できるロードマップを用意しました。法律・安全・機材・撮影手順・AI解析・見積もり・納品まで、段階ごとにやさしく説明します。専門用語はかならず解説し、各章に初心者事例・ステップ手順・具体ツール操作・注意点コラム・ケーススタディを入れています。
初心者事例(最初の一歩)
- ドローン未経験・写真経験少なめ。
- 予算は10〜30万円。
- 週末だけ活動。地元のJA、自治体窓口、猟友会に顔つなぎが可能。
→ 本記事の手順で**“はじめの有料トライアル1件”**を獲ることが現実的な目標です。
手順(この記事の使い方)
- 全体像をつかむ(章1)。
- 法規・安全の下地を固める(章2)。
- 機材と予算を決めて最低限のセットを揃える(章3)。
- 撮影計画〜フライト〜データ整理の型を覚える(章4)。
- AI解析で“価値のある図と数字”を出す(章5)。
- 見積・納品テンプレで案件化(章6〜7)。
具体ツール操作(最初に触ってほしい無料系)
- 地図確認:国土地理院地図・Google Earthで地形と空域の当たりをとる。
- 飛行可否の目安:メーカーのFlySafe/GeoMap(例:DJI FlySafe)や自治体の公表資料で確認。
- 共有:Googleスプレッドシートで案件管理テンプレを複製。
注意点コラム(法規は“最新”を確認)
無人航空機のルールや申請窓口の運用は随時更新されます。**国土交通省の公式サイト/DIPS(申請・登録関連)**で最新の公告・手引きを確認し、地元警察・自治体・管理者の個別ルールも必ずチェックしましょう。夜間飛行・目視外飛行・人口集中地区などは、追加の許可・承認が求められる場合があります。
本文
第1章 仕事の全体像とスキルセット
害獣調査副業のゴールは「意思決定に使える地図と数字」を出すことです。単なる“綺麗な空撮写真”ではなく、出没位置・個体数目安・移動ライン・出没時間帯の傾向など、対策につながるアウトプットが求められます。
初心者事例
- 里山の畑でイノシシの被害。電気柵の設置前に“どこから来ているのか”を知りたい。
- 猟期外の巡回で“群れの寝床”と“水場”のあたりをつけたい。
- 町内の通学路近くでシカの出没が増え、時間帯とルートを把握したい。
手順(全体フロー)
- ヒアリング:被害内容・場所・時期・頻度・危険箇所の情報収集。
- 計画:地図上で探索エリア・待機位置・離発着場所を決定。
- 許可・連絡:管理者や自治体へ事前周知、必要なら申請。
- フライト:安全確保・撮影(可視+必要に応じてサーマル)。
- データ整理:写真・動画・位置情報をフォルダ分け。
- AI解析:検出・カウント・ヒートマップ化。
- レポート:地図・図表・考察・推奨対策をまとめ納品。
- アフターフォロー:1〜3か月後のモニタリング提案。
具体ツール操作
- ヒアリング表(Googleフォーム)を用意。項目例:場所URL、被害作物、出没時間、足跡・糞・掘り返しの場所、隣接の水場や藪。
- KML/GeoJSONで境界線を共有(Google Earth/マイマップ → 共有リンク)。
- チェックリスト(スマホ)で当日の安全確認・機材確認を記録。
注意点コラム(“動物を追い詰めない”)
調査の目的は被害軽減であって追跡や威嚇ではありません。繁殖期・子連れは特にストレスを与えない運用を。関係法令・ガイドライン・地域の慣行を尊重し、野生動物保護の視点を常に持ちましょう。
ケーススタディ
小規模農家×週末フリーランス:被害畑の周辺500mを夜明け前に可視+サーマルでサーチ。足跡が集中する藪の切れ目と水路沿いの浅瀬を特定。電気柵の開口部と水路越え対策を提案し、翌月の被害件数が半減。継続モニタリングを月額1万円で受注。
第2章 法規・安全・保険の基礎
ドローンは航空法・電波法・道路交通法・各自治体条例・私有地管理規程など、複数のルールに関わります。ここでは具体の数字に踏み込みすぎず、考え方と行動順序を押さえます。
初心者事例
- 「どこで申請が必要?」がわからず、撮影日が決まらない。
- 人がいない山林でも、近くに道路・電線・送電設備があり不安。
手順(安全・法務の型)
- 最新ルールを一次情報で確認(国土交通省サイト、DIPS、メーカーのフライトマップ)。
- 飛行場所の管理者に連絡(農地・山林・河川・ため池など)。
- **特別な飛行(夜間・目視外等)**が絡む場合は必要な許可・承認の要否を確認し、余裕をもって手続き。
- 保険(対人・対物、可能なら機体・賠償特約)に加入。
- 安全体制:見張り(スポッター)配置、立入り禁止テープ、誘導灯、無線連絡手段。
- 危険予測:風・突風、地形風、電波妨害、鳥・獣との距離。
- 飛行ログ保存:日時・高度・コース・天候・離発着点。
具体ツール操作
- DIPS関連サイト:登録・申請・管理(最新の手順は公式解説に従う)。
- フライトマップ:飛行禁止・制限エリアの確認、NOTAM(航空情報)もあれば確認。
- リスクアセスメント表(テンプレ):想定危険→予防策→当日の点検項目をチェック。
- 無線機/メッセンジャー:見張りとの連絡系統を事前にテスト。
注意点コラム(夜間・サーマル運用)
夜間は周囲との誤認や接触のリスクが上がります。照明・発光機、離着陸帯のマーキング、見張りの反射ベストなどを必須装備に。サーマルは“熱源”を拾いますが、人・家畜・車両への配慮を徹底します。
ケーススタディ
学区近接の里山:通学路に近い斜面でシカが出没。日中は目視巡回、夕方は目視内で低高度のサーマルスキャン。学校・自治会へ事前周知、安全管理者を配置。1週間で出没時間帯のピーク(18–19時台)を特定し、見回り強化の時間帯を提案。
第3章 機材選びと予算設計
害獣調査は**“見る”ための光学と、“位置を正しく記録する”測位が肝です。はじめは可視光カメラ+堅実な機体からでも十分。将来的にサーマル(熱赤外)やRTK(高精度測位)を加えると夜間・広域・精度が強化されます。
比較早見表(例)
| 用途 | 機体タイプ | カメラ | 強み | 弱み | 目安予算 |
|---|---|---|---|---|---|
| まずは昼間捜索 | コンシューマー機 | 1インチ可視光 | 低コスト・取り回し | 夜間は弱い | 10〜20万円 |
| 夜の出没確認 | サーマル搭載機 | 熱赤外+可視 | 夜間・藪越しに強い | 高価・重い | 40〜100万円 |
| 広域マッピング | RTK対応機 | 可視(場合によりND) | 精度高いオルソ作成 | 設定が増える | 30〜80万円 |
※価格・入手性は変動します。購入前に最新情報を確認してください。
初心者事例
- 予算15万円:まずは昼間の巡回+夕方の斜光時間に可視光で足跡・掘り返しを記録。
- 予算50万円:中古/リースを活用してサーマルに挑戦。獣道の推定精度が上がる。
手順(購入〜初期設定)
- 用途優先度を明確化(昼間>夜間、広域>点検、静止画>動画)。
- 機体選定:バッテリー本数、プロペラ・フィルター、風耐性、静粛性。
- アクセサリー:折り畳み発着シート、ランディングライト、誘導灯、反射ベスト、予備SD、耐候ケース。
- 初期設定:ファーム更新、ホームポイント、RTH高度、ジンバル調整、カメラ設定(写真はRAW+JPG)。
- テストフライト:広場で離着陸→ホバリング→直線移動→緊急停止を繰り返して操作感を掴む。
具体ツール操作(例:ミッションアプリの基本)
- 自動飛行ミッション:グリッド(格子状)を描いて高度・重なり率を設定。
- カメラ:シャッター優先orマニュアル。NDフィルターでシャッタースピード1/1000前後を確保しブレを抑える。
- ログ:フライトログをクラウド同期、後でQGISに読み込む準備。
注意点コラム(“静かな運用”は信頼を生む)
害獣調査は地域密着。離発着や車両の停車場所、住民への声かけ、作業音、撤収の清潔さなどふるまいが評価に直結します。朝夕の時間帯には特に配慮しましょう。
ケーススタディ
町内会の依頼:畑と竹林が入り組むエリアで早朝フライト。広角・ズームを併用し、田畦の切れ目に複数の獣道を確認。**比較写真(Before/After)**を作り、柵の設置位置が絞れたと評価。
第4章 撮影計画とフライト手順(可視+サーマル)
調査の質は計画8割。風、太陽高度、地形、動物の生活リズムを掛け算して**“勝ちやすい時間帯”**を選びます。
初心者事例
- イノシシの掘り返しが増えた畑。夜明け前〜早朝が出没ピークと聞いた。
- ため池周辺でシカの足跡。夕暮れに水を飲みに来る可能性が高い。
手順(現場オペレーション)
- 事前偵察:地図で風の抜ける谷、障害物(電線・樹木)、離発着帯をチェック。
- 安全ブリーフィング:役割分担(操縦・見張り・記録)。緊急時の着陸場所も共有。
- ミッション設定:
- 広域サーチ:高度60–100mで等間隔のグリッド、重なり率は高め。
- ピンポイント:足跡・糞・泥の付着など“サイン”の上を重点サーチ。
- サーマルの使い方:
- 昼:日照で地面が暖まるとコントラスト低下。朝夕が狙い目。
- 夜:人・家畜・車両と誤認しやすい。距離・動き・周辺状況で判別。
- 記録:写真は地点名+連番で命名、動画は短いクリップに分割。
- 撤収:周辺清掃・近隣への挨拶。要望があれば1枚速報地図をその場で見せる。
具体ツール操作(例)
- ミッションアプリで矩形選択→高度・速度・重なり率を入力→往復/縦横を選ぶ。
- サーマル表示:白熱/黒熱/等高線風などパレット切替で視認性を上げる。
- ウェイポイント:疑わしい地点に自動往復経路を作って反復観察。
- メモ:スマホの地図アプリにピン+写真を添付。
注意点コラム(“見つけられない日”もある)
動物は生き物。毎回バシッと映るわけではありません。**兆候(掘り返し・足跡・糞)と環境要因(風・水・斜面)から“出る確率が高い場所マップ”**を作れば、実務的な価値は十分あります。
ケーススタディ
棚田エリアのイノシシ:夜明けのサーマルで2頭を遠距離で確認。取付道の合流点に出没が集中。地形図に獣道ラインを描き、柵のゲート位置の再設計を提案。設置後、「水田の踏み荒らしゼロ」を報告。
第5章 データ整理とAI解析(検出・可視化)
撮っただけで終わらせないために、**“見える化”**を最速で回す仕組みをつくります。
初心者事例
- 写真・動画がごちゃつき、どれがどこの地点かわからない。
- サーマルの点が動物かどうか判断に迷う。
手順(整理→解析→可視化)
- フォルダ設計:
案件名/日付/Raw-写真/動画/サーマル/現地写真/レポート。 - メタ情報付与:撮影時間、緯度経度、天候、レンズ、備考(足跡・糞・掘り返し)。
- AI検出(例):
- 既成の物体検出モデルをクラウドで試す。
- 結果の誤検出は人が確認し、閾値を調整。
- GIS可視化:
- QGISで地図へレイヤー化(検出点、足跡、被害箇所)。
- ヒートマップで出没密度を表示。
- レポート:サマリー1枚+詳細の2段構成でPDF化。
具体ツール操作(例)
- WebGIS/QGIS:CSV(緯度経度付き)をドラッグ&ドロップ→スタイルでアイコン変更→ヒートマップ作成→KML出力。
- AI検出:小規模ならクラウド推論に画像を投げ、**置信度(確からしさ)**のスライダーで調整。
- 動画分割:長尺は区間切り出ししてアップロード負荷を減らす。
注意点コラム(“AIは補助輪”)
AIの結果は提案であり決定ではありません。環境ノイズ(温排水・日射・岩の蓄熱)で誤検出が起きます。現地知(足跡、獣道、糞)の情報と突き合わせて総合判断しましょう。
ケーススタディ
渓谷のシカ:AI検出の点群が谷筋に並ぶ。地図で尾根越えルートを重ねると、鞍部(あんぶ)に集中。自治体に通行止め時間帯と看板を提案。翌月に人身被害の苦情がゼロに。
第6章 見積・納品・契約の型
副業を“仕事”に変えるのはドキュメントの整備です。料金の根拠と成果物の定義を明確にしましょう。
初心者事例
- “いくらでやれますか?”と聞かれて固まる。
- 納品物のイメージが合わず手戻りが多い。
手順(見積と納品の定義)
- パッケージ化:
- ライト:半日/可視のみ/レポ1枚。
- スタンダード:1日/可視+サーマル/レポ6〜10P。
- モニタリング:月1回×3か月/簡易比較レポ。
- 構成費目:準備・移動・飛行・解析・レポート・保険・許認可対応。
- 成果物:PDFレポ(サマリー+詳細)、KML/GeoJSON、主要写真(JPG)、動画(短編)、レイヤー凡例。
- 契約:キャンセル規定、天候順延、データの二次利用可否、秘密保持。
- 請求:着手金(30–50%)+納品後残金/自治体は請求書・納品書・検収書の様式に従う。
具体ツール操作(例)
- 見積テンプレ(スプレッドシート)で人日×単価、交通費、保険、機材償却を自動計算。
- レポートテンプレ(Googleスライド/Canva):表紙→地図→検出結果→所見→提案の順で固定。
- 電子契約:クラウド契約サービスで相手の捺印フローを短縮。
注意点コラム(“価格は説明可能に”)
単価の高低より、なぜその価格かが説明できることが重要です。安全・許可・解析・納品整備は目に見えにくいコスト。見積に内訳を記すと納得されやすい。
ケーススタディ
自治体の試行導入:スタンダードプランで5万円台のトライアルを実施。迅速なレポ1枚速報が評価され、翌年度の**年間モニタリング(毎月)**に採択。
第7章 継続案件化とスケールの方法
単発で終わらせない工夫が副業の安定化につながります。
初心者事例
- 毎月の依頼にしたいが、成果の見せ方が難しい。
- 一人作業の生産性が頭打ち。
手順(継続化)
- KPIの合意:被害件数/面積、出没頻度、柵破損箇所、通報件数など。
- 定点比較:同ルート、同高度、同設定で月1回。比較図をテンプレで更新。
- アラート運用:出没が増えたら通知し、臨時便の提案。
- チーム化:スポッター・ドライバー・解析担当の分業。
- 地域連携:JA・猟友会・学校・自治会へ小さな成果報告会を開催。
- 拡張:獣害から倒木・法面・ため池の点検へ派生。
具体ツール操作(自動化の芽)
- フォーム→スプレッドシートで通報を自動集計→地図にリアルタイム描画。
- クラウドストレージで案件フォルダをコピーテンプレ化。
- 定型レポは図の差し替えで10分更新。
注意点コラム(“過度な期待管理”)
ドローンとAIは魔法ではありません。可能なこと/できないことを最初に伝え、誤検出・空振り・天候理由の延期も含めた現実的な運用を合意しましょう。
ケーススタディ
山間の学校区モニタリング:通学路に近い谷筋を月2回サーベイ。出没ヒートマップを掲示板に公開し、地区の見回り時間と照明点灯時間を調整。人身事故ゼロを継続、次年度も契約更新。
FAQ(5〜8問)
Q1. ライセンスや申請は必須ですか?
A. 飛行方法や場所によって必要な登録や手続きが異なります。国土交通省の最新情報と管理者のルールを確認し、必要なら許可・承認を取得してください。
Q2. まず買うならどんな機体が良い?
A. はじめは可視光の信頼できる機体+バッテリー2〜3本でOK。夜間や藪越しを重視するならサーマル機を検討。最初から高価な構成にしなくても、案件化してから段階的に拡張できます。
Q3. サーマルで人や家畜を誤認しませんか?
A. します。サイズ・動き・場所の文脈で判断し、目視確認と追加撮影を組み合わせてください。AIの閾値も現場ごとにチューニングが必要です。
Q4. 1件あたりの作業時間は?
A. ライトで半日、スタンダードで1日+解析0.5〜1日が目安。移動距離・申請・天候で大きく変わります。
Q5. 料金の相場は?
A. 地域差が大きいですが、半日:数万円〜、サーマル+レポで**数万円台後半〜**が一つの目安。保険・申請・移動を含めるとコストが嵩むため、内訳の明示が大切です。
Q6. 解析は難しくない?
A. テンプレ化すれば難度は下がります。QGISでのポイント表示、ヒートマップ、KML出力を覚えれば、実務で通用する絵が作れます。
Q7. データの扱いで注意点は?
A. 個人情報・営巣・希少種など、公開を控えるべき情報があります。納品データの公開範囲や保管期間を契約で取り決めましょう。
Q8. 失敗しても取り返せますか?
A. 取り返せます。撮影ログと反省メモを残し、次回の時間帯や高度・経路を変えて再挑戦。比較図を作ると改善が見えます。
まとめ
AI×ドローンの害獣調査副業は、地域の課題解決に直結し、やりがいも収益性も両立しやすい分野です。成功の鍵は、
- 安全と法規を最優先にする姿勢、
- 計画8割の徹底、
- **AI解析で意思決定に役立つ“図と数字”**を出すこと、
- パッケージ化とテンプレ整備で再現性を高めること。
最後に小さな実践プランをもう一度。
- 昼間の可視光機でテスト → 2) ヒートマップ付きレポを1件作る → 3) 自治体・JA・猟友会に実績として見せる → 4) サーマル機を導入して夜明け・夕暮れのサーチへ拡張。
この流れなら、初心者でも1〜2か月で初案件に手が届きます。地元のフィールドで、安全第一の調査から始めてみましょう。